Voyager
Mike Oldfield
wea 0630-15896-2
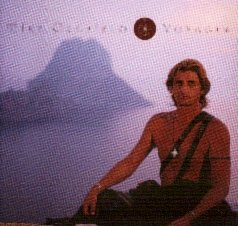 The Song of the Sun (Bieito Romero)
The Song of the Sun (Bieito Romero)
Celtic Rain (Mike Oldfield)
The Hero (traditional arrangement by Mike Oldfield)
Women of Ireland (traditional arrangement by Mike Oldfield)
The Voyager (Mike Oldfield)
She Moves through the Fair (traditional arrangement by Mike Oldfield)
Dark Island (traditional arrangement by Mike Oldfield)
Wild Goose Flaps Its Wings (Mike Oldfield)
Flowers of the Forest (Traditional arrangement by Mike Oldfield)
Mont St Michel (Mike Oldfield)
つまるところ、マイク・オールドフィールドは作曲家なのだと思う。
ロックというものが単なる音楽のジャンルに留まらず、一つの文化にまで発展しているからには、ロック・ミュージシャンが様々な側面を持っているのは当然だ。その証拠に「ロックンローラー」という言葉は、ロックの演奏者とか作曲者とかいうものを越えた、もっと幅広い意味合いで捉えられている。例えば、楽器も弾かず歌も唄わないでロックンローラーであることは充分に可能なのだ、確かに。しかし、その中にあって、マイク・オールドフィールドほど「曲を作る」という作業そのもので純粋に評価されて来たロックンローラーは、かつていなかったのではなかろうか。
デビュー作の「チューブラー・ベルズ」から今回の「ヴォイジャー」に至るまで、マイク・オールドフィールドが一貫して守って来た姿勢は、ある一つの楽器、あるいは楽器群に対するこだわりを持たないということであった。彼は、もしもプレイヤーとして何に当たるのかといえば、もちろんギタリストであろう。実際、彼が他の人の曲にゲストとして参加する時は、そのほとんどがギタリストとしてしてだ(ブラム・チャイコフスキーのアルバムは、例外中の例外)。そしてまた、彼は実は、とてつもないテクニシャンである。渋谷公会堂の日本公演に於いて、特に「オマドーン」で見せたギター演奏は、クラシックの奏法に根差したすさまじいものであった。
ところが、その技量から考えた場合、マイク・オールドフィールドは驚くほど演奏家として語られていない。もちろん彼を好きな者が聴けばすぐわかる独自の音を持ってはいるのだが、それに対する言われ方も、巧いというよりは、その作った曲と同じく「美しい」だ。これは例えば、キース・エマーソンが、そのほとんどの評価をプレイヤーとして受けているのと対称的である。彼の演奏を聴いた人は、「とにかく、EL&Pは楽器が巧い(すごい)」と言う。曲の構成や詩の意味などの、作曲技法としての評価はその後だ。そしてまた、(少なくとも初期のころは)作品のほとんどはそのままステージに持ち込んでもすぐに演奏できそうな構成を取り、ライブは曲芸さながらであった。
もちろんこれは、EL&Pの作曲が下手だということではない。かれらはそれほど、プレイヤーとしての側面が重要だというだけである。また、パンクやニューウェイヴとか言われた人達のように、その文化的背景や発言内容の方が大切なこともあるし(「グレイト・ロックンロール・スウィンドル」で、マルコム・マクラレンは「レコードが内容で売れたらお終いだ」といっていた)、場合によってはそれらもどうでもよくて、容姿やかっこよさのみで売っている人もいる。同様にしてマイク・オールドフィールドは、何よりもその作った曲が主にあるロックンローラーなのだ。
EL&Pは演奏する為に曲を作る。マイク・オールドフィールドは、作った曲を聴かせるために演奏している。どちらがいいということではなく、それが彼らの個性である。
だから、先に書いた通り、彼は楽器にこだわらない。時には平気でギターを捨てるし、民族楽器や古楽器、電子楽器、オーケストラなどを必要に応じて取り入れる。アルバムを発表するごとに、完全な一人演奏だったり、かなりの共演者をやとったり、バンドになったり、オーケストラが入ったりするが、それも大した問題ではない。彼にとって共演者とは、たまたまその時必要になった楽器の一つに過ぎないのだから。
さて、その彼のリリースした曲の中にも、さまざまなカヴァー・ヴァージョンがある。デビュー作「チューブラー・ベルズ」にしてからが、その最後に「セイラーズ・ホーンパイプ」を置いてその後のトラッド小品群の前哨になっているし、ロッシーニ、ヴィヴァルディ、ガーシュイン、タルレガなどのクラシック、数は少ないがアバやシャドウズなどのポップス系もその中に加えられている。これらは、作曲家マイク・オールドフィールドの編曲の腕の見せ所だ。そもそも作曲と言うのはメロディを作ることではない。きちんと編曲して演奏出来るところまで持っていって初めて完全な作曲である(そんなことは、タンジェリン・ドリームやピンク・フロイドの曲を聴けばすぐわかる)。だからこそ、モーツァルトやショパンにも「〜の主題による変奏曲」などという「作曲」があるのだ。
新作「ヴォイジャー」は、マイク・オールドフィールドの感性がいささかも鈍っていないことを示す力作であった。岩場のような場所に海(湖かも知れない)を背景にして彼自身が座っているというジャケットそのもののような大地への賛歌が、古楽器や現代の電子楽器、あるいはオーケストラを交えて壮大に語られる。そして、10曲中6曲までが自作以外の曲の編曲であり、それらの間に自分の曲を挟むという構成を採っている。にもかかわらず、違和感はまったくない。小品を集めて一つにしたというようなものではなく、あくまで一つのテーマに沿って創り上げたコンセプトアルバムだ。これは、前作「遥かなる地球の歌」に対する「この身近なる地球の歌」とでもいうところであろう。「チューブラー・ベルズ」から一貫して語られて来た「この世界への想い」とでもいうものが、ここでもまた見事に音楽化されている。やはり、並々ならぬ力量の持ち主なのだと、改めて敬服するばかりである。
作曲家マイク・オールドフィールドは、これからどこに向かって航海をしていくのだろう。20年以上に渡って彼の曲を追い続けたが、まだまだこの旅は終わっていないようである。
(宇宙暦28年8月30日)
「遥かなる地球からの歌」に戻る
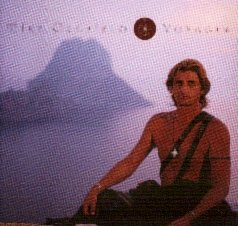 The Song of the Sun (Bieito Romero)
The Song of the Sun (Bieito Romero)