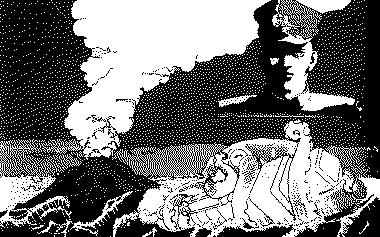一、発進! 原子力潜水艦「伊吹」
「あっ、あれはなんだ」武雄は、ようやく霧の晴れてきた東の方角をゆびさした。
「どうしたの、タケオ」
「マリア。ほら、あれ」
タケオのゆびさしたほうを見て、マリアはあっと声を上げた。波の向こうに、真黒な島が不気味な影を見せているのである。
「どうして、今まで見えなかったのかしら」
「霧のせいだよ。この辺は、海流がぶつかるから、霧が深いんだ」
それは見れば見るほど不気味な島だった。ここからはよくみえないが、全体を原生林がおおっているのだろう、濃い緑色の地肌が暗く沈んでいる。真中には大きな火山があって、そこからたなびく煙が黒雲のように太陽をさえぎっていた。
「じゃあ、あれがパパのいる所なのね」
「そうだね」
一ヶ月前、マリアの父親のジョーンズ博士は、この近くの海で行方不明になっていた。ジョーンズ博士は、海洋学の世界的に有名な科学者だったが、船でアメリカに向かう途中、このあたりで嵐に巻き込まれたのである。しかし、最後の通信で近くの島に向かうということだけは伝えてきた。どこの島かとたずねると、たった一言「どくろ」という返信がかえって来た。
「タケオ。どくろって、なんのことかしら」
「さあ、ぼくにはわからないな」
とそのとき、誰かが二人の肩をポンとたたいた。ふり向くと、この原子力潜水艦「伊吹」の艦長、黒岩五郎だった。
「艦長」
「どうやら、ついたらしいな。あれが我々の目的地、どくろ島だ」
「どうして、どくろ島というんですか」
「わからん。ジョーンズ博士の最後の言葉から取ったんだ。レーダーによると、このあたりに島はあれしかない。だから、ジョーンズ博士はあそこにいることになる」
二人はもう一度どくろ島のほうを見た。武雄は、いやな予感がした。
「さて、それでは二人とも中に入りたまえ。島の偵察に入ろう」
「はい!」
原子力潜水艦伊吹は、武雄の父・伊吹博士と、マリアの父ジョーンズ博士が設計した、全長二百メートルの万能戦艦である。ハイマンガンスチールの船体は海底五万メートルの水圧にも耐え、あらゆる状況で百パーセントの能力を発揮できるようになっている。これは、日本政府が新しく設置した海洋開発省の要請で作られたものだが、その本当の性能はこれから少しずつ、読者諸君の前に明らかにされていくだろう。
「あ、艦長」
三人が指令室に入っていくと、若い背の高い男がレーダーから顔を上げた。副長の犬塚だった。
「犬塚君。F体制に入ってくれたまえ。島のまわりを一周する」
「了解」
「クロイワさん、F体制ってなんですの」
「おや、ジョーンズ博士はマリアさんに伊吹のことをなにもいわなかったのかい」
「ええ」
「では、見ていたまえ。今二人をびっくりさせてあげるから。よし、浮上!」
「浮上!」
とたんに伊吹の船体がグラリとゆれた。窓の外を見た二人は、アッとおどろいた。
伊吹が空を飛んでいる!
読者諸君。これこそが、伊吹の秘密能力のうちの一つなのだ。
「どうだ、すごいだろう。伊吹は反重力装置で空を飛べるんだ。さあ、島に行くぞ」
伊吹は、ロケットのようなスピードで島に向かい出した。武雄とマリアは、ただただおどろくばかりである。
「でも艦長、なぜ最初から空を飛んでこなかったんですか。そのほうが速いのに」
「燃料のウランがたくさんいるからね。近くまでは海を来たんだが、とにかく今は島がどんな所か見なくちゃいけない」
「タケオ、あれを見て」
「うん、なんだい」
「ほら、あの火山」
「どれどれ。あっ!」
マリアにいわれて火山のほうを見たみんなは、あっとおどろいた。山の中腹に、大きな人間の頭ガイコツのような物が浮き出ているのだ。
「そうか、それでジョーンズ博士は、どくろといったんだ」
「でも、あれはなんなのでしょう。自然にできたんでしょうか」と犬塚がいった。
「わからない。とにかく、着陸だ。犬塚君、どこか適当な場所はないか」
「西の方に、入江のような所があります」
「よし、そこに行こう」
黒岩艦長の命令に、伊吹は西の入江に向かった。
そこは、まさに天然の船着場であった。細長い桟橋のような岩があり、伊吹はそこにおりた。
しかし、それが思わぬ危険を呼ぶことになろうとは、よもや誰も思わなかったのである。
「よし、上陸だ」
「いよいよ、ジョーンズ博士を探しに行くんですね」
「うむ、武雄君。君は病気の伊吹博士のかわりに来たんだ。責任は重いぞ」
「はい」
「よし、それでは上陸部隊を作ろう。私と、第一当直班の五人、それに武雄君だ。犬塚君には、まさかの時のためにここに残ってもらう」
「わかりました」
「クロイワさん、私もつれてって下さい」
マリアが、つと前に進み出た。しかし、艦長はこういった。
「マリアさんには、この近くの木や草で食べられるものをさがしてもらう。もう、船内食にはみんなうんざりしているからね」
「まあ」
「ただし、絶対に一人では行かないこと。それに、伊吹からあまり離れてもいけない。わかったね」
「はい」
「よし、それでは上陸部隊のメンバーは、ミラクルガンをつけたまえ。使い方は、わかっているな」
ミラクルガンは、伊吹博士の発明した秘密兵器である。
「さあ、出発だ」
そのとき――。
伊吹の船体がガタンとゆれた。なにか、大きな物がぶつかったらしい。
「どうしたんだ」
「あっ、艦長。あれを見て下さい」
犬塚の声に外を見たみんなは、再びあっとおどろいた。
なんと全長百メートルはあるかと思われる大ダコが、伊吹に巻きついているのだ。
「いかん、空に逃げるんだ」
「だめです。あいつがしっかり伊吹をつかんでいます」
「くそっ、どうしたらいいんだ」
海の中でなければ、魚雷はつかえないのだ。
と、そのとき、マリアが叫んだ。
「クロイワさん、そこの赤いスイッチを。早く!」
「なんだって」
武雄がさっと飛び出すと、マリアのいうとおりにした。とたんに、外から、
「ぎぇあああ」という恐ろしい悲鳴がきこえた。
「船体に、電気を通しました。もう大丈夫ですわ。ほら!」
そのとおり、タコはずるずると離れていった。そして、ザザザと音をたてて海に沈んだ。
「一体、どういうことなんだ」
武雄がスイッチを切りながらいった。
「マリア、どうして君はこのスイッチのことを」
「わからないわ。ただ、イブキが危ないって思ったら」
「どうやら、ジョーンズ博士のやったことらしいな」
腕を組みながら、黒岩艦長がいった。
「博士は、伊吹の初航海には、必ずマリアさんをつれて行くようにいっていた。きっと、特殊な催眠教育でマリアさんの頭の中に、伊吹の性能を植えつけたんだ」
「そういえば、パパが私の頭に電極をつないで眠らせたことがあります」
「うむ、きっとそれだ。よし、それならいよいよマリアさんには伊吹に残ってもらわなくてはいかん。犬塚君、あとをたのむぞ」
「了解」
こうして、武雄たちはジャングルに向かって出発することになった。
二、怪しいタイコ
「あら、あれはなにかしら」ふとマリアは、花を摘む手を休めて顔を上げた。
入江には、伊吹の船体が黒々とその雄姿を見せている。ちょうどそれと反対の方角にあたる森の中から、トントンとおかしな音が聞こえて来るのだ。
マリアが首をかしげていると、そばにいた伊吹の乗組員がマリアにいった。
「マリアさん、船にもどりましょう」
「あれは、原住民が通信につかうタイコです」
とたんに、彼は声もなくたおれた。見ると、背中に粗末な木の矢が突き刺さっている。
「きゃっ」
悲鳴をあげて伊吹にもどろうとするマリアの前に、黄色い恐ろしい顔があらわれた。
マリアは気を失った。
「艦長。これから、どっちに行きましょうか」と、武雄がいった。
「うむ、君はどう思う?」
「南に向かうべきだと思います」
「なぜだね」
「あのガイコツ・マークは、南からしか見えないからです。ジョーンズ博士は、『どくろ』といったんだから、南から上陸したのではないでしょうか」
「えらい! よく気がついたな。他には、何かないかね」
「人間は水がなくては生きられません。だから、南のほうにある河のそばに、ジョーンズ博士はいると思います」
「よし、そっちに行こう。しかし武雄くん、すばらしい推理だな」
「いや、なに、初歩的なことですよ、艦長」
と、そのとき――。
トントントン、トントントン。
森の中から、怪しいタイコの音が聞こえて来た。
「やっ、あれはなんだ」
トントントン、トントントン。
「行ってみましょう」
「待ちたまえ。念のため、ミラクルガンをパラライザーにセットしておくんだ」
「はい」
「よし、行こう」
七人は、手に手にミラクルガンをかまえて、怪しい音のする方向に向かった。そして、ついにその正体を突きとめて、あっとおどろいた。
「マリア!」
「ジョーンズ博士もいるぞ」
なんと、七人が歩いて来た森の向こうは広場になっていて、そこにはいなくなったジョーンズ博士が、マリアといっしょに柱にしばりつけられているのだ。まわりには、ギラギラ光るヤリを持った原住民たちが、ぐるぐるとおどりまわっている。
トントントン、トントントン。
あの音は、原住民たちのたたくタイコの音だったのだ。
「大変だ、助けなくちゃ」
「まあ待て。もう少し、ようすを見よう」
七人が森の中からのぞいていると、一人の強そうな男が進み出た。
「カーッ。ヨミカ、ヨミカ。エマタリモマ、ヲラレワ」
男は、マリアとジョーンズ博士の前で両手をあげると、何やら叫び出した。
「艦長、なんていってるんでしょうね」
「さあ、よくわからんが、あいつは酋長かなにからしいな。おそらく、二人をいけにえにしようというのだろう」
「えっ、それは大変だ。助けましょう」
「よし、次にあいつが何かいったら飛び出すぞ」
艦長の言葉に、あとの六人はミラクルガンをにぎった。
と、そのとき――。
「ウョチウュシ。ダンヘイタ、ダンヘイタ。タレマカ、ニビヘクド、コスムノウョチウュシ」
「ニナ。ダンヘイタ、ハレソ」
一人の原住民がかけて来て何か叫んだかと思うと、急に村中がさわがしくなった。
「どうしたんだろう」
七人があっけにとられていると、そこに一人の少年が運ばれてきた。その顔立ちは、どことなく武雄に似ている。しかし、ぐったりとして元気がない。
「ルスウド、ルスウド。ウマシデンシ、ハデママノコ」
酋長は子供をだきかかえてオロオロしている。どうやら彼の息子らしい。
「艦長、わかりましたよ」
隊員の一人が叫んだ。
「きっと、あの子供がケガか何かしたんですよ」
「なるほど」
原住民たちは、もう完全にマリアたちのことを忘れているようだった。ただ、ウロウロするばかりである。
武雄はそこにいるみんなにたずねた。
「みなさんの中に、医学を知っている人はいませんか」
「なんだって?! まさか――」
「そうです。助けてあげるんです」
この言葉に、他の六人は互いに顔を見合わせた。やがて、一人がおずおずといった。
「私は、医者をやったこともあるが」
「よし、行こう。武雄君のいうとおり、見殺しにはできん。もしかしたら、マリアさんのためにもなるかも知れんしな」
七人は手に手にミラクルガンをかまえて、森を出た。
「おい、助けてやるぞ」
黒岩艦長の声に、原住民たちがいっせいにふりむいた。他の時ならおそいかかってきたかも知れないが、今はそれどころではない。それに、彼らの顔はどことなく日本人に似ているようであった。
「タケオ!」と、柱にしばられていたマリアが叫んだ。
「待っててくれ、マリア」と、武雄がいった。
さっきの、元医者だった隊員が子供の顔を調べ出した。やがて彼は、足首に小さなキズを見つけた。
「艦長。ジャングル蛇にかまれています。このままだと、死んでしまいます」
「なおるか」
「万能解毒剤を飲ませてみましょう」
彼は、ポケットから白い丸薬を出すと、少年の口に入れた。少年は、しばらくうめいていたが、やがてうっすらと眼をあけた。
「もう、だいじょうぶです」
「タッオナ」
「タッオナ」
原住民たちはおどろいてわめき出した。酋長も立ち上がって武雄たちを見ていたが、やがて右手をさし出した。
「ウトガリア。タレクテケスタ、ヲコスム、チタタナア」
黒岩艦長はがっしりとその手をにぎり返した。そして、自分を指して、
「クロイワ」といった。酋長は少し考えてから、やがて自分をさして、
「オサマ」と答えた。
三、大怪獣アクロン
「あれだよ、艦長」ジョーンズ博士が火山をゆびさした。そこには、あの奇怪などくろが、もうあと五百メートルの所にせまっていた。
「私がつかまっている間に原住民たちの言葉を覚えて聞き出したところによると、あのどくろの中に大変な秘密があるらしい」
「アクロン、アクロン」
そばには、あのジャングル蛇にかまれた少年がついていて、何かを叫んでいる。酋長のオサマが、火山までついていくようにいったのだ。
「アクロン? なんのこと、パパ」と、マリアがいった。
「彼らの神らしい。いや、悪魔というべきか。あのどくろの口から出て来て、彼らをさらうんだそうだ。私たちは、アクロンをしずめるための生けにえだったんだよ」
「アクロン、イキオオモテット」
「はは、そうだったな。アクロンは、なんでもその辺の木より大きいらしい。二百メートルぐらいかな」
「じゃ、伊吹と同じぐらいですね」
「そうなるな。それで、オサマ酋長は私たちならアクロンをやっつけられると思って、シロヒに案内させたんだ」
シロヒというのは、さっきの原住民の子供の名前である。
「ジョーンズ博士。それなら、伊吹を呼んでおいたほうが良くありませんか」
「それもそうだな。通信機はあるんだろう」
「はい、さっき犬塚君にマリアさんと博士のことをいっておきました」
「よし、それならばこうしよう。まず伊吹をこの上空五百メートルの所に呼んで、反重力光線でマリアを回収してもらう」
「それで」
「マリアがのっていれば、伊吹はその能力を百パーセント出せるだろう。あとは、残ったわれわれだけでアクロンをおびき出すんだ」
「わかりました。伊吹を呼びます」
黒岩艦長は腕時計につけた通信機の発信ボタンを押した。伊吹を呼ぶためのものである。やがて、西から巨大な空飛ぶ潜水艦が姿をあらわした。
「じゃ、マリア。先に行っててくれ」と武雄がいった。
「タケオ、死なないでね」
「わかってる」
伊吹から、淡いむらさき色の光線が発射され、マリアはその中を伊吹に向かってのぼって行った。
「さあ、行くぞ!」
七人は、ミラクルガンを右手に持つと、引き金ダイヤルをレーザー光線に合わせた。後からは、シロヒとジョーンズ博士がついてくる。どくろの口はもう眼の前である。
「艦長、待ちたまえ」
どくろの入口の直前まで来た時に、ジョーンズ博士が叫んだ。そして、どくろの歯にじっと見入った。
そのどくろマークは、高さが約三百メートル、人間の顔の千三百倍である。したがって、歯だけで十メートルはある。ジョーンズ博士は、その歯の表面を調べてからこういった。
「これは、地球の物質ではない」
「なんですって」
「みたまえ。地球にはない金属だ。これは、どういうことなんだろう」
「とにかく、入ってみましょう」
「うん」
七人はミラクルガンを歯と歯のすき間に向けて発射した。やがて、人間が入れるぐらいの穴が開いた。
「行くぞ」
九人は黒岩艦長を前にして、その空洞の中に入って行った。
「思ったより暗くないな」
艦長がつぶやくと、
「あれのせいですよ」と武雄が答えて後をゆびさした。他の八人がふりむくと、あのどくろマークの眼と鼻の所が、ちょうど明りとりの窓になっているのだった。
「なるほど。それで南向きにしたんだな。しかし、そうするとこの空洞は天井が三百メートルもあることになる」
と、その時――。
「アクロン!」
シロヒが叫んだ。はっとして、シロヒのゆびさした方を向いた八人は、そこに巨大な魔神像を発見してあっとおどろいた。
「やっ、これはなんだ」
それは、たしかに身の丈二百メートルはありそうな、日本の埴輪に似た像だった。
「アクロン、アクロン」
シロヒは狂ったように叫びつづけている。しかし、そのアクロンの像はまったく動くようすはなかった。
「どういうことなんだ。これがアクロンとかなら、どうして村をおそうんだろう」
「ただの、石像じゃないか。シロヒ、カアクロンガレコ(これがアクロンか)」
「ダウソ(そうだ)」
「ううむ。よし、調べてみよう」
九人は、ミラクルガンを手にして、その石像に近づいた。やはり、何かが起きる気配はなかった。
「博士、これはなんですか」
武雄の声に一同が近づくと、アクロンの足元に一枚の金属プレートがはってあった。文字のような物がかいてある。
「なになに。ややっ、これは地球語ではないぞ。宇宙語だ」
「なんですって」
「待ちたまえ。少しなら読めるから。ええと、『我ら、アクロン星人、ここに不時着す。宇宙船の乗員の体はすべて破壊された。よって、我ら、我らの脳を使い、サイボーグの石像を作る。これを用いて、この星の住民をさらい、我らの体とする』」
「そんなバカな!」
「ふむ、それで住人をさらうんだな。だとすると、どこかにさらわれた者がとらえられているはずだが」
「博士、こっちにボタンがあります」
隊員の一人が見つけたスイッチを押すと、一方のかべが開いて、小さな部屋があらわれた。
「ややっ」
「アッ、ダチタトヒタレワラサ、ハレコ(これは、さらわれた人たちだ)」
中には、ガラスの入れ物が立ち並び、さらわれた原住民たちが入れられていたのである。
「まだ生きてますか」
「奴ら、体をつかうつもりだと書いていたから、多分大丈夫だろう。ほら、ここにスイッチがある」
ジョーンズ博士がかたわらのスイッチを押すと、ガラスの容器がスルスルと開き、中の人たちが眼を覚ました。
「どうやら、こいつはタイム・ストッパーの一種らしいな。中の時間を止めて、物を保存するんだ。大変な科学力だ」
「さ、逃げましょう」
「うむ」
九人と、シロヒに説明をされた原住民たちは、さっきの穴に向けて一斉に走り出した。と、そのとき――。
「アークローン!!」
石像は眼をピカリと光らせると、とてつもなく大きな声で、叫んだのである。
「大変だ、うごき出したぞ」
石像はゆっくりと立ち上がると、みんなの方に手をのばしはじめた。
「よし、ミラクルガンで撃つんだ。シロヒたちは早く出ろ」
武雄たちはアクロンに向けて、ミラクルガンを発射した。アクロンは一瞬ひるんだが、すぐにまた手をのばして来た。
「だめだ、とても勝てない。黒岩艦長、伊吹を呼ぶんだ」
「わかりました。犬塚君、犬塚君」
黒岩艦長が通信機に向かって叫ぶと、すぐに答が返って来た。
「はい、艦長」
「われわれは今、アクロンと戦っている。どくろの口から一人ずつ出るから、すぐに回収してくれ」
「わかりました」
「艦長、私にも通信機を! 犬塚君、マリアを出してくれ」
「はい」
「パパ!」
「マリア。どうすればいいかわかってるな」
「はい、M体制ね」
「そうだ。用意をしておけ。ただし、われわれが行ってからだぞ」
「ええ」
すでに洞穴の中には、ジョーンズ博士と武雄と黒岩艦長しかのこっていなかった。
「よし、武雄君出たまえ」
「でも」
「早くするんだ」
「はい」
いわれたとおり、武雄は穴から外に飛び出した。
「アークローン!!」
石像の叫び声はすぐうしろだ。と思ったとたん、武雄の体は反重力光線にとらえられ、宙に浮かび上がった。
四、どくろ島の最後
伊吹の中は大さわぎだった。もうすぐ、アクロンとの決戦である。その前に博士と艦長を救わねばならない。「タケオ!」
「マリア!」
ブリッジに入ったとたん、マリアは武雄に飛びついてきた。
「パパは?」
「すぐに来る。それよりも戦闘準備をしなくちゃ」
「今、M体制にうつる用意ができた所よ」
「なんだい、M体制って」
「見ててちょうだい」
「博士と艦長、回収おわり」
インターフォンから声がした。
「よし、戦闘開始!」と犬塚が叫んだ。
「見て!」
マリアの声に、窓の外を見たみんなは、どくろの口がガーッと開き出したのを見て、あっとおどろいた。
「出てくるぞ」
ドアがバタンと開いて、黒岩艦長とジョーンズ博士が入ってきた。
「そら来た。ミサイル発射」
空中の伊吹から四発のミサイルが飛んで行き、どくろに当たって爆発した。やっつけたか。
「ああっ」
読者諸君! なんと恐ろしいことだろうか。爆発の煙がおさまってみると、そこにはアクロンがなんにもなかったかのように立っているのだ。
「やはりだめだったか。マリア!」
「はい、犬塚さん、そこの青いボタンを」
「これですね」
犬塚がボタンを押すと、伊吹の船体がゆれはじめた。何が始まるのだろうか。
「見たまえ、武雄君」
博士にいわれて外を見た武雄はあっとおどろいた。
地面には伊吹の影が写っているのだが、それが序々に人間の形へと変わって行くのだ。
読者諸君! これこそが伊吹の最大の秘密である。M体制とは、伊吹を身長二百メートルの巨大なロボットに変えることだったのだ。
「着陸!」
ズシン、と伊吹がゆれる。地面におりたのである。
「さあ、しっかりつかまってろよ。黒岩艦長、まかせたぞ」
「わかりました」
艦長は伊吹のハンドルをにぎった。伊吹はズシンズシンとアクロンに向かって歩き出した。
「サブマリン・パンチ!」
伊吹は右手でアクロンをたたいた。アクロンはぐらりとよろめいた。
「サブマリン・キック!」
左足がアクロンにたたきつけられる。
「よし、もう少しだ。サブマリン・チョップ!」
伊吹の左手の攻撃に、アクロンの右手がふっとんだ。
「アークローン!!」
「くそ、まだ参らないのか」
とたんに伊吹の船体がグラリとゆれた。
「ああっ」
なんと、アクロンは残った左手で、伊吹の右手をもぎ取っていたのである。
「いかん!」
「どうしますか、博士」
「よし、最後の手段だ」
「パパ、あれを使うの」
「そうだ。あいつに勝つには、Q光線をつかうしかない。艦長、その緑のボタンを押したまえ」
「これですね」
黒岩がスイッチを入れると、伊吹の胸からパラボラ・アンテナのような物が出て来た。
「よくねらうんだぞ。Q光線は一発しかないんだ」
「わかりました」
黒岩艦長は伊吹の動きを止めた。アクロンは勝ちほこったかのように近づいてくる。
「発射!」
黒岩艦長が叫ぶと、伊吹の胸から強烈な水色の光が飛び出してアクロンに命中した。
「やった!」
アクロンはぴたっと動きを止めた。腹に「Q」の字の形に穴があいている。
「あぶない」
艦長は伊吹をいきなり後に下げた。とたんにアクロンは左手を上げたかと思うと、ドサーッとたおれた。
「勝ったぞ。しかし――おそろしい奴だった」
「ん? 変だな」
武雄がつぶやいた。たしかにおかしい。伊吹の船体がゆれている。
「あっ、あれを見て」
マリアの声に外を見たみんなは、こんどこそ本当にあっとおどろいた。
どくろ火山が爆発している!
「いかん。自爆装置がついていたんだ。島がしずむぞ。オサマたちにしらせなくては」
「よし」
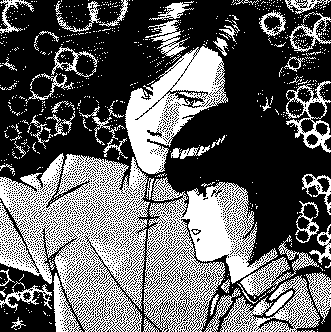 伊吹はM体制のままオサマたちの所に向かった。M体制の伊吹を見たオサマたちは大さわぎだったが、シロヒがマイクで、
伊吹はM体制のままオサマたちの所に向かった。M体制の伊吹を見たオサマたちは大さわぎだったが、シロヒがマイクで、「ウガチ、ウガチ。タカミ、レコ。ヨムズシガマシ、トイナゲニクヤハ(ちがう、ちがう。これ、味方。早く逃げないと、島が沈むよ)」と伝えたので、あわてて海に逃げ出した。何人か逃げおくれた者は、伊吹が残った左手ですくい上げた。
「早く、早く」
もう、島はどこもかしこも火を吹いていた。伊吹と島の人たちのカヌーは、あわてて島をはなれた。
「アークローン!!」
島からはおそろしい叫び声がする。
「なんでしょう、あれ」
「あいつはまだ、完全にやられたわけじゃないんだな」
「アークローン!!」
その声も、武雄たちが島をはなれるにしたがって遠くなり、やがてすっかりと聞こえなくなった。
「これであの島の秘密も解けなくなったな」と、ジョーンズ博士がいった。伊吹と島の人たちは、千メートルぐらいはなれた所で止まり、島をふり返った。
「ええ、考えてみれば、かわいそうな宇宙人でしたね」
「そうだな。しかし、他人の体をぬすむなんてことは、やはり許されない。正義は必ず勝つんだ」
「あ、島が沈むわ」
そのとおり、どくろ島は最後の大爆発を起こして、ゆっくりと海の中に消えていくところだった。
「オサマや、シロヒはどうするのかしら」
「なあに、近くに別のもっといい島があるさ。アクロンなんて怪物のいない」
「そうね」
マリアは、そっと武雄によりかかった。どくろ島はもうすっかりと姿を消し、あとには一筋の煙がたなびいているだけであった。
読者諸君! これで伊吹の最初の冒険はおわりである。このあと、伊吹はどうなったであろうか。また、黒岩艦長は、武雄は、マリアは――。
伊吹のような万能戦艦が、なんの事件にもであわぬはずはない。きっとまた、新しい冒険があるはずである。
それでは諸君。
もしも機会があったら、「続・原子力潜水艦伊吹――謎の円盤編隊の巻」で、再びお会いすることにしよう。